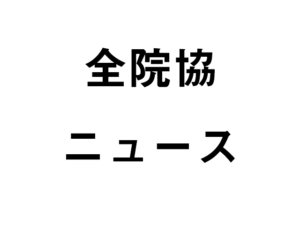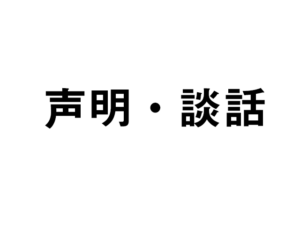全院協ニュース
全院協ニュース第250号を発刊しました
タグ一覧:中央大学, 名古屋大学, 国会, 大学改革, 学費・奨学金, 就職問題, 文科省, 理事校会議, 財務省, 院生自治会・院生協議会紹介
2017.03.18
目次
- 巻頭言
- 2016年度省庁・議員要請の報告
- 要請概要
- 文科省要請
- 財務省要請
- 各班からの報告
- 参加者からの感想
- 要請行動を振り返ってみて
- 院生自治会・院生協議会紹介
- 第3回理事校会議の報告
- 編集後記
巻頭言
今年度、ようやく給付型奨学金が誕生することとなった。だが、大きな問題もある。それは、第一に大学院生が除外されていることである。第二に給付型奨学金の先行実施分は2800人、全学生のたった0.35%にすぎないこと、2018年度も2.5%で対象も2万人であること。住民税非課税世帯は文科省試算でも6.1万人であり、その3分の1にすぎない。経済的に進学が困難な者を後押しするためと謳うが、実際は全国に約5000校ある高校から学校の成績や部活動に応じて1~2名程度推薦するという。これでは貧困対策にすらなっていない。加えて、部活動をやるにも成績を上位に保つために塾へ通えばその費用もかかる。私は中学・高校で吹奏楽部に入っていたが、毎月の部費500円のほか、演奏会衣装やコンクール出場、そのための合宿でさらに別途お金を徴収される。国は経済的に苦しい家庭にはこうした部活動などに費やす余裕がない、ということを見ていないとしか思えない。第三に、文科省はレクチャー当時大学院生にも財源を見て拡充していきたいとしていたが、議論の推移はいつの間にやら19-22歳の特定扶養控除縮小や大学院生の奨学金貸与額上限規制、奨学金返還に関する成績要件による減免規定の縮小で財源をまかなおうとする方向になっていることである。まさに学生・院生の中に分断を持ち込もうとする動きであり、私たちの教育を受ける権利・学習権をさらに侵害するものといわねばならない。
このような中、2月に政党・議員への要請行動を行った。今回は、自民党を除くすべての政党・会派が政党要請に応じるという、数の上では画期的な要請行動となった。詳しくは各班の報告を参照していただきたい。一面では選挙が近いという政治情勢の問題もあるが、他面では参議院選挙においてすべての党が給付型奨学金を公約に掲げたことからうかがい知ることができるようにローンと化し、サラ金並みの取り立てを行う日本の劣悪な学費奨学金制度が社会問題として認知されてきたことの証左でもある。
給付型奨学金を大学独自に進めようとする動きもあるが、この原資は授業料の値上げでまかなわれようとする例が多い。学費を負担する保護者や学生からすれば取られ損である。加えて、軍学共同の動きが加速し、「大学改革」によって民主的運営が切り崩されつつある。「決められる政治」の本質はこれまでのところ「勝手に決める政治」でしかない。その悪弊はここでもみられるのである。この間の「改革」によって雇用条件や研究環境は悪化の一途をたどっている。私たちは「自分には関係ない」と無関心でいてはならない。後々私たちに返ってくる問題だからである。
2016年度全国大学院生協議会議長 土肥有理